広島市東区、活気ある広島駅のほど近くに、荘厳な社殿を構える広島東照宮(ひろしまとうしょうぐう)があります。
この神社は、天下人・徳川家康(とくがわ いえやす)を神として祀る東照宮の一つです。
しかし、不思議に思いませんか?
関ヶ原の戦いで徳川家と敵対し、大敗を喫した毛利家がかつて治めた土地に、なぜ徳川家康の神社が建てられたのでしょうか?
この記事では、広島東照宮の創建に秘められた、当時の広島藩主・浅野家の複雑な思惑と、その歴史の真実を紐解いていきます。
広島城主交代:毛利氏から浅野氏へ
慶長5年(1600年)、天下分け目の関ヶ原の戦いが勃発しました。
西軍の総大将として敗れた毛利輝元は、領土のほとんどを没収され、長年治めた広島の地を追われることになります。
代わって広島に入国したのが福島正則でしたが、後に改易(領地没収)されます。
その次に入国したのが、徳川家康の信任が厚い浅野長晟(あさの ながあきら)でした。
その後、家康の孫娘と結婚した彼の嫡男、浅野光晟(あさの みつあきら)が二代目広島藩主となります。
徳川家康を神として祀る東照宮が創建されたのは、この二代藩主・光晟の時代です。
毛利氏に代わって広島を治めることになった浅野家にとって、東照宮の創建は、重要な意味を持っていたのです。
浅野光晟の決断:東照宮創建に込められた政治的思惑
光晟が東照宮を建てた背景には、以下のような政治的・戦略的な理由がありました。
- 徳川幕府への忠誠心の誇示: 広島は、かつて徳川家康と敵対した毛利氏の本拠地でした。ここで東照宮を建立することは、幕府に対する浅野家の揺るぎない忠誠心を示す、最も明確な方法でした。
- 領民の結束と平和への祈り: 荒れ果てた戦国の世を終わらせ、泰平の世を築いた家康の御威光を借りて、広島の街の安定と繁栄を願う意味合いも込められていたと伝えられています。
東照宮は、広島城の北東、鬼門の方角に位置しています。
これは、城下町全体の守護を祈願する、風水的な意味合いも持っていました。
広島の歴史を語る、静かなる証人
広島東照宮は、創建から幾度もの災害に見舞われ、特に昭和20年(1945年)8月6日の原子爆弾投下で、社殿のほとんどを焼失しました。
しかし、人々の手によって再建され、今もなおその威厳ある姿を保っています。
この神社は、徳川家康の魂を伝えるだけでなく、戦国の世が終わり新しい時代を迎えた広島の複雑な歴史を、静かに見守り続けているのです。
広島東照宮を訪れることは、単なる参拝ではなく日本の歴史の大きな転換期を肌で感じることのできる、貴重な体験と言えるでしょう。
※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、建物、商品などとは異なる場合があります。
広島東照宮
住所:〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里2丁目1−18
公式HP:https://www.hiroshima-toshogu.or.jp/
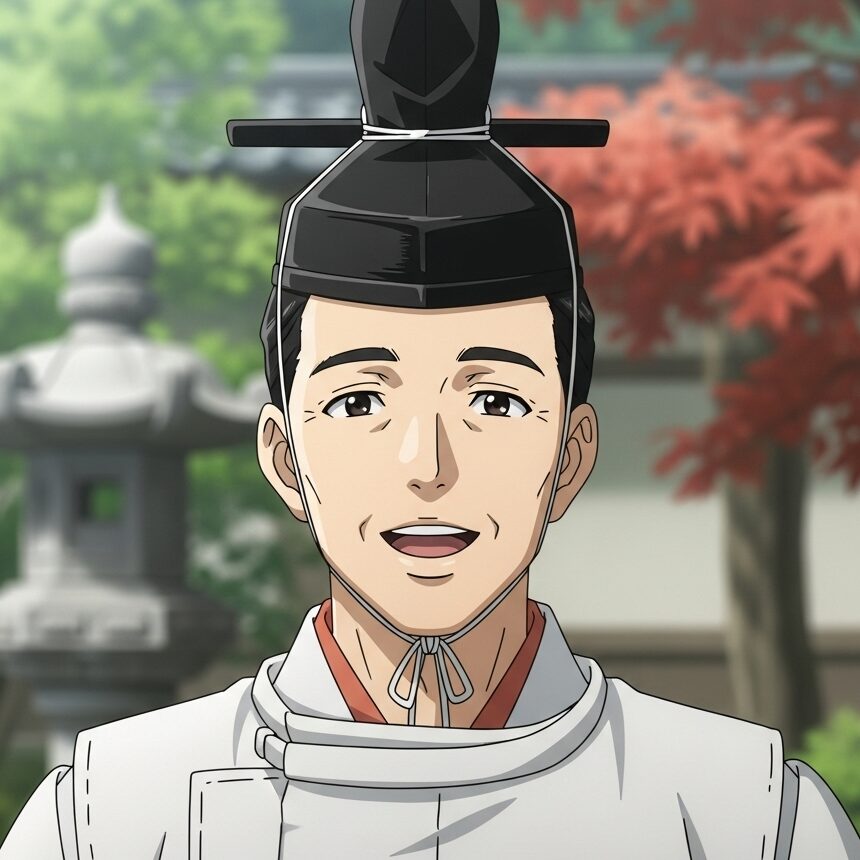
広島東照宮の創建は、新時代への順応と藩の永続を願う浅野家の知恵と覚悟の表れです。
広島の歴史の転換期を見守り、平和を祈り続けるという深き思いが、社殿に込められています。


コメント