広島の平和記念公園からほど近く、広島城の敷地内に鎮座する広島護国神社(ひろしまごこくじんじゃ)。
多くの参拝者が訪れるこの神社は、ただの観光地ではありません。
そこには、原爆の悲劇を乗り越え、平和への願いを込めて再建された、深い歴史が刻まれています。
この記事では、広島の街と共に歩んできた護国神社の物語をご紹介します。
原爆投下と社殿の焼失
広島護国神社の始まりは、明治元年(1868年)。
戊辰戦争で命を落とした広島藩の藩士たちを祀るために創建された、「水草霊社(すいそうれいしゃ)」がその前身です。
その後、幾度かの改称を経て、明治34年(1901年)に現在の広島護国神社の名称となりました。
しかし、その歴史は悲劇に見舞われます。
昭和20年(1945年)8月6日、原子爆弾が投下された際、神社は爆心地からわずか300mほどしか離れておらず、社殿は全焼。
境内は壊滅的な被害を受けました。
多くの尊い命と共に、神社の歴史も一度は途絶えてしまったのです。
平和への願いを込めた再建
戦後、焦土と化した広島の街で、市民たちは懸命に復興を進めました。
護国神社もまた、市民や関係者の熱意によって再建への道が開かれます。
当初は、被爆した元の場所で再建が検討されました。
しかし土地の整備計画の都合上、昭和31年(1956年)に現在の広島城跡へ移転し、再建されることになりました。
これは、過去を乗り越え、新しい広島のシンボルとして生まれ変わることを意味していました。
再建された社殿は、市民からの寄付を中心に建立されたものです。
- 社殿: 昭和33年(1958年)に完成。日本の伝統的な建築様式を踏襲し、落ち着いた佇まいです。
- 参道と鳥居: 参拝者が通る道は、平和への願いを象徴するように、清らかに整備されています。
被爆遺構

広島護国神社の境内には、原爆の爆風と熱線に耐え倒壊せずに残った、「大鳥居」「石灯ろう」「狛犬」「標柱」があります。
これらは、戦争の悲惨さを静かに語りかける「生きた証人」です。
広島護国神社は、広島の歴史を象徴する場所です。原爆で一度は失われながらも、市民の力で再建され、今もなお平和の願いを発信し続けています。
広島城を訪れる際には、ぜひ広島護国神社にも足を運び、その深い歴史と平和への祈りに触れてみてください。
※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、建物、商品などとは異なる場合があります。
広島護国神社
住所:〒730-0011 広島県広島市中区基町21−2
公式HP:https://www.h-gokoku.or.jp/
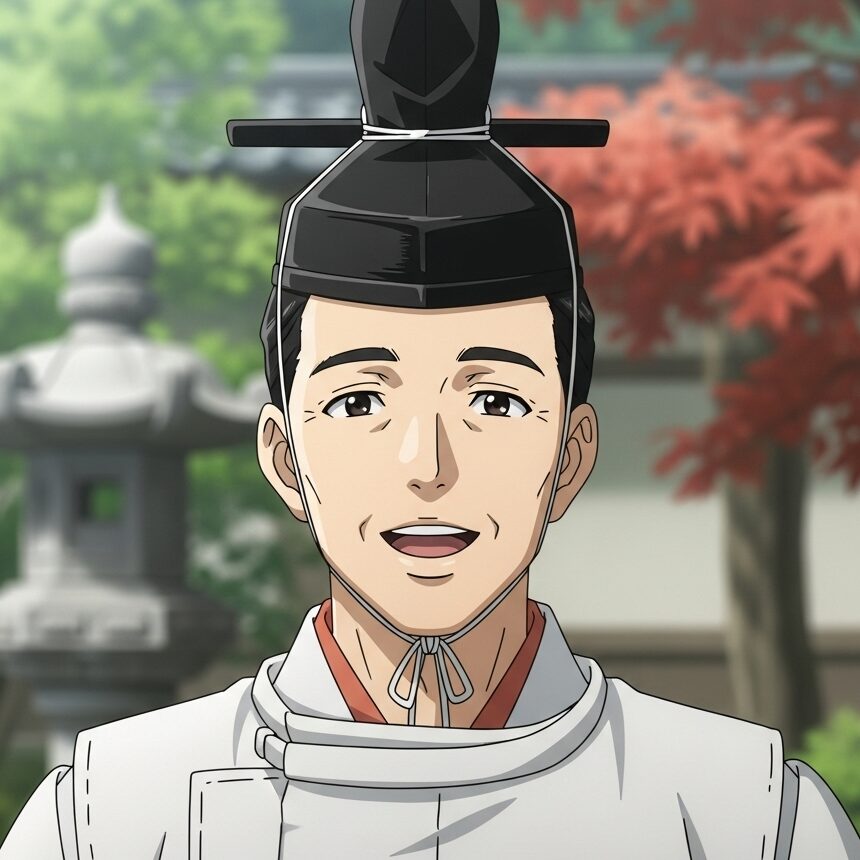
広島護国神社は、戦災で一度はすべてを失いました。しかし爆風に耐え、奇跡的に生き残った樹木たちが、再建を願う人々の心の支えとなったのです。
その歴史はただの悲劇ではなく、困難な時代を生き抜いた人々の、平和への強い願いそのものなのです。


コメント