潮の満ち引きに合わせて、海に浮かぶようにその姿を変える「厳島神社(いつくしまじんじゃ)」。
世界遺産にも登録されたこの美しい景観は、多くの人々を魅了し続けています。
この壮麗な海上社殿を造営したのは、平安時代末期に武士として初めて太政大臣に上り詰めた、平清盛(たいら の きよもり)です。
彼の厳島神社への信仰は、広く知られています。
しかし清盛がこの場所に託したのは、信仰心だけではありませんでした。
この記事では、厳島神社が「海の文化都市」へと変貌を遂げた、平清盛の知られざる偉業について紐解いていきます。
京から海へ:文化人・清盛の思惑

当時の都、京都は日本の政治・文化の中心地でした。
雅やかな貴族文化が栄え、武士である清盛もその影響を強く受けていました。
彼は、瀬戸内海を掌握し「日宋貿易(にっそうぼうえき)」で莫大な富を築くことで、平家一門の権勢を強めていきます。
その拠点として目をつけたのが、瀬戸内海の交通の要衝にある「厳島」でした。
清盛は厳島神社を再建するだけでなく、都の文化をこの地に持ち込むことを計画しました。
これは単に信仰心からくる行いではなく、「平家の権威を内外に示すため」の政治的な意味合いも持っていたのです。
厳島神社に集められた文化の粋

仁安3年(1168年)頃に清盛は、厳島神社の大改修を行います。
清盛が厳島神社に持ち込んだ文化は、多岐にわたります。
- 社殿建築: 寝殿造りと呼ばれる当時の貴族の邸宅様式を取り入れ、海上社殿を造営しました。これは、都の雅な文化を地方の神社に取り入れた画期的な試みでした。
- 美術工芸品: 経典や調度品、武具など、一門が誇る最高の技術と財力を結集させた美術工芸品を数多く奉納しました。中でも、平家一門の繁栄を願って奉納された『平家納経』は、平安時代を代表する国宝として知られています。
- 舞楽: 清盛は大阪の四天王寺から舞楽を厳島神社に伝来させました。現在も厳島神社で行われている舞楽は、当時の文化を今に伝える貴重な伝統芸能です。
これらの偉業は、清盛が当時の最高権力者として、文化的な側面にも力を注いでいたことを示しています。
彼は厳島を、都の文化を地方に発信する拠点として、そして平家の繁栄を象徴する「海の文化都市」として発展させたのです。
平家滅亡後も受け継がれた偉業
寿永4年(1185年)3月24日に平家が滅亡し、清盛が築き上げた栄華ははかなく散りました。
しかし厳島神社はその後も守られ、多くの人々に信仰され続けました。
清盛が造営した社殿や奉納した文化財は、毛利元就など後世の権力者によっても大切にされ、今日までその姿を留めています。
厳島神社は、平清盛の栄枯盛衰を静かに見守り続けてきただけでなく、彼が文化人として成し遂げた偉業を今に伝える「歴史の証人」でもあるのです。
※この記事に掲載している画像はイメージです。実際の団体、個人、建物、商品などとは異なる場合があります。
厳島神社
住所:〒739-0588 広島県廿日市市宮島町1−1
公式HP:https://www.itsukushimajinja.jp/
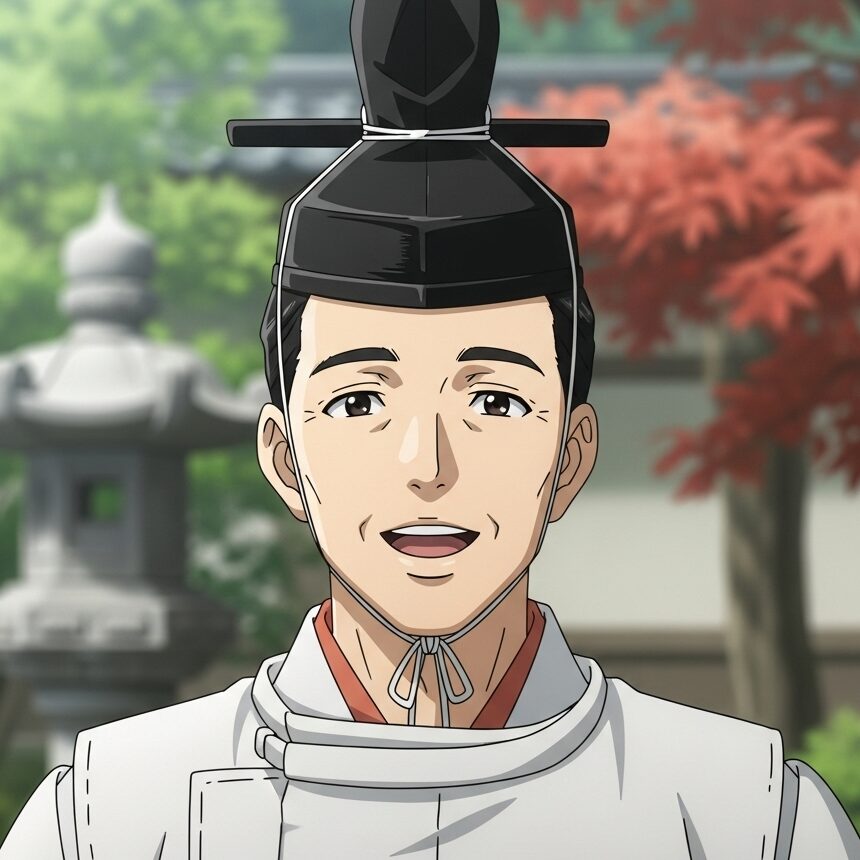
清盛公は、神の御力を借りて権威を高めると同時に、都の雅を海上に再現し、新たな文化拠点を作り上げられました。
厳島神社は、清盛公の先見の明と文化的センスを示す、永遠の傑作と言えましょう。



コメント