戦国時代に九州地方の覇権をめぐり、長年にわたって対立を続けていた毛利氏と大友氏。
両者の関係に大きな転機をもたらしたのが、大内輝弘の乱(おおうち てるひろのらん)です。
この乱は毛利氏にとって危機となり、大友氏との関係を決定づける歴史の分岐点となりました。
今回は、この乱が両家の覇権争いにどのような影響を与えたのかを紐解いていきます。
大友氏が仕掛けた「謀略」

大内輝弘は、毛利氏によって滅亡に追い込まれた名門・大内氏の血を引く人物でした。
彼は豊後国(現在の大分県)の大名・大友宗麟(おおとも そうりん)によって擁立され、大内氏の再興を狙い挙兵します。
なぜ輝弘は挙兵に踏み切ったのか。
その背景には、大友氏が仕掛けた「謀略」が存在していました。
策士・吉岡長増の「神算」
永禄12年(1569年)5月、毛利氏と大友氏による、北九州の覇権をかけた戦いが始まります。
毛利氏の圧倒的な攻勢を前に、大友氏は危機的状況に陥っていました。
この危機を打開するため、大友氏の重臣である吉岡長増は、宗麟にある策を進言します。
それは、毛利軍を九州から引き剥がす「後方攪乱」でした。
その中核を担う存在として目を付けられたのが、大友氏のもとに身を寄せていた大内輝弘でした。
大友氏は「輝弘を山口へ送り込み、毛利の統治に不満を持つ旧大内家臣たちを蜂起させる計画」を立てます。
さらにこの動きは、同年6月に出雲国で挙兵した「尼子再興軍」の動向とも呼応するものでした。
山口炎上:高嶺城攻防戦

10月、輝弘は毛利氏が支配する周防国(現在の山口県東南部)に上陸し、挙兵します。
大内軍は山口へと侵入。高嶺城(こうのみねじょう)の攻略を開始します。
大内遺臣が次々と加わり、山口へ侵攻する頃、その軍勢は6千にまで膨れ上がっていたとされています。
山口へなだれ込んだ大内軍により、周辺の寺院の多くが焼かれました。
毛利氏は軍勢の大半を北九州の戦線へ投入していたため、山口の守備は手薄となっていました。
高嶺城主の市川経好も九州へ出陣中で、城にはわずかな城兵しか残されていませんでした。
しかし、死力を尽くして徹底抗戦する城兵たちに大内軍は苦戦。
大軍を擁しながらも、高嶺城を陥落させることはできませんでした。
毛利氏の迅速な対応と乱の鎮圧
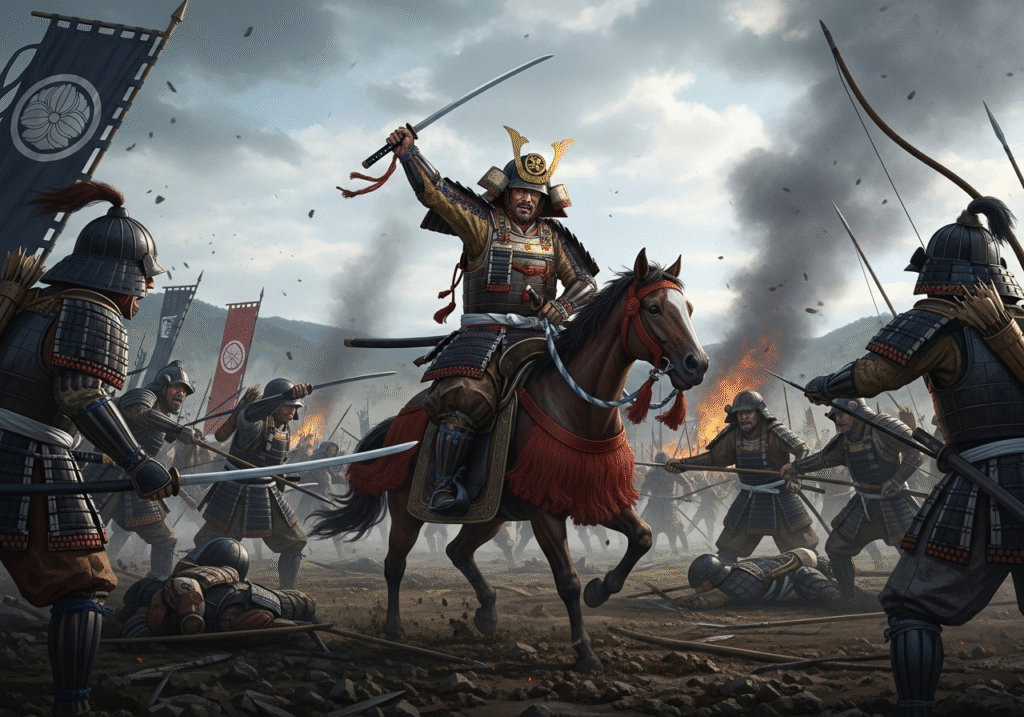
この乱は、毛利氏を一時的に窮地に陥れました。
しかし毛利氏は迅速な対応を見せ、窮地を脱します。
毛利元就はただちに毛利軍へ九州からの撤退を命じ、反乱軍の鎮圧を最優先事項としました。
「尼子再興軍の挙兵」「大内輝弘の乱」と、領内の反乱が相次いで起きたため、元就は強い危機感を抱いたのです。
これを受け、吉川元春らは山口へと急行します。
彼らは大内輝弘の軍をわずか数日で打ち破り、乱を鎮圧。
輝弘は自害に追い込まれました。
乱の鎮圧には、以下の点が大きく影響しました。
- 毛利元就の迅速な判断
- 吉川元春の軍事手腕
- 毛利氏の家臣団の結束力
- 大友氏にとって大内輝弘は、捨て駒にすぎなかった
乱が変えた両家の関係
この乱を通じて毛利元就は、大友氏が自家を脅かす最大の敵であることを再認識しました。
一方で大友氏も、毛利氏の結束力と元就の求心力、そして元春の卓越した軍事手腕を思い知らされます。
大内輝弘の乱は、大友氏が仕掛けた「一発逆転」の賭けであり、毛利氏と大友氏の関係を大きく変えることになりました。
中国地方での支配を盤石なものにします。一方で、一部を残し、九州の拠点を失いました。
その後、織田信長との対決に軸足を移し、九州進出から手を引きました。
毛利軍を撤退させることに成功。毛利氏に奪われていた筑前国(現在の福岡県)の領地を回復。
その後、毛利氏との戦いはなくなり、龍造寺・島津氏との九州の覇権争いへ移り変わりました。

この一件こそ、両雄が運命を分かちし大乱であった。
大友家の策は巧妙なれど、元就殿の迅速な判断と元春殿の武勇が勝敗を分けた。


コメント